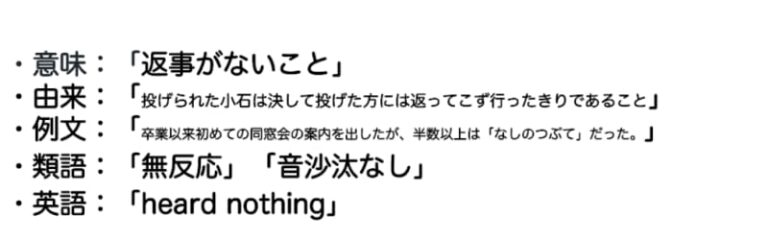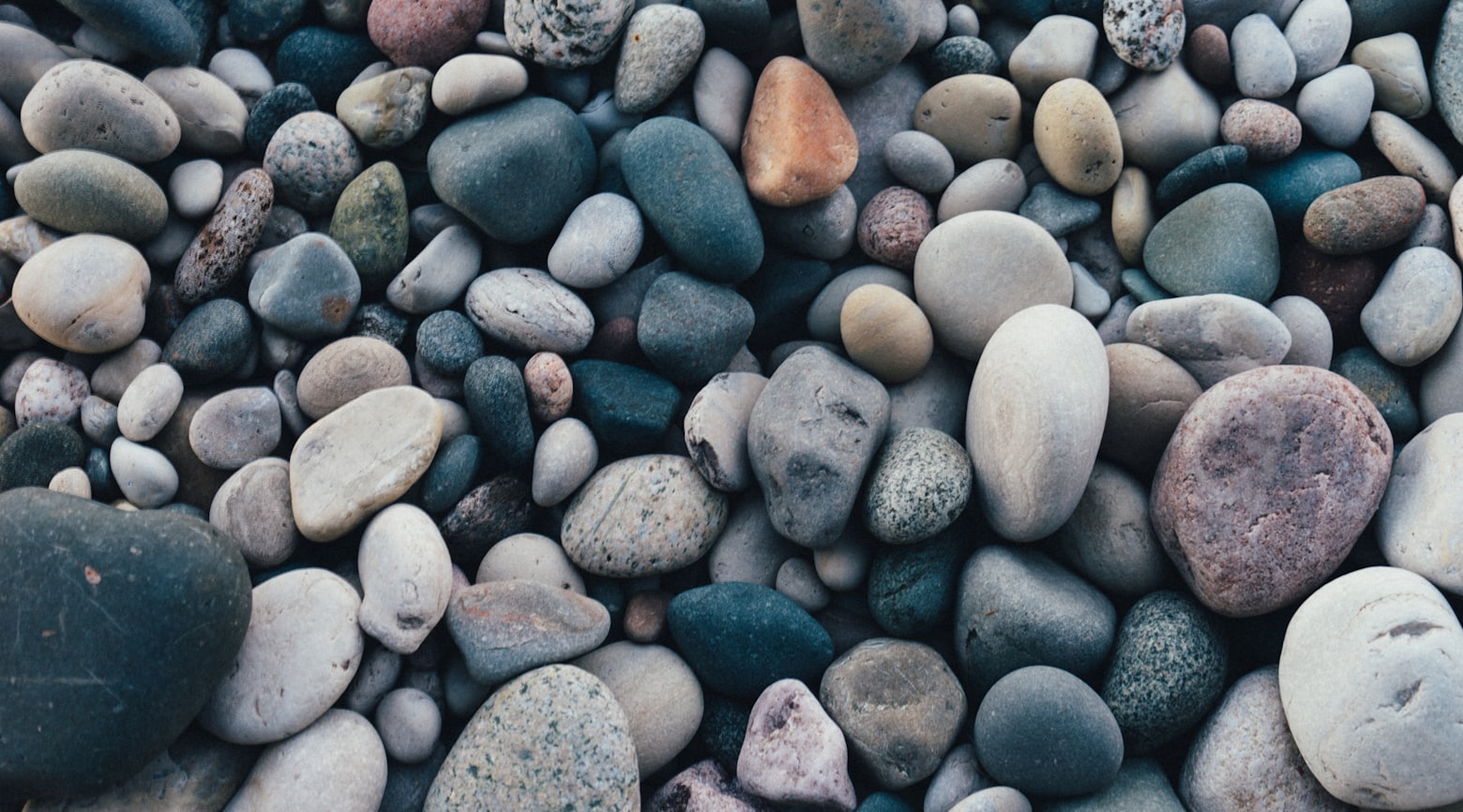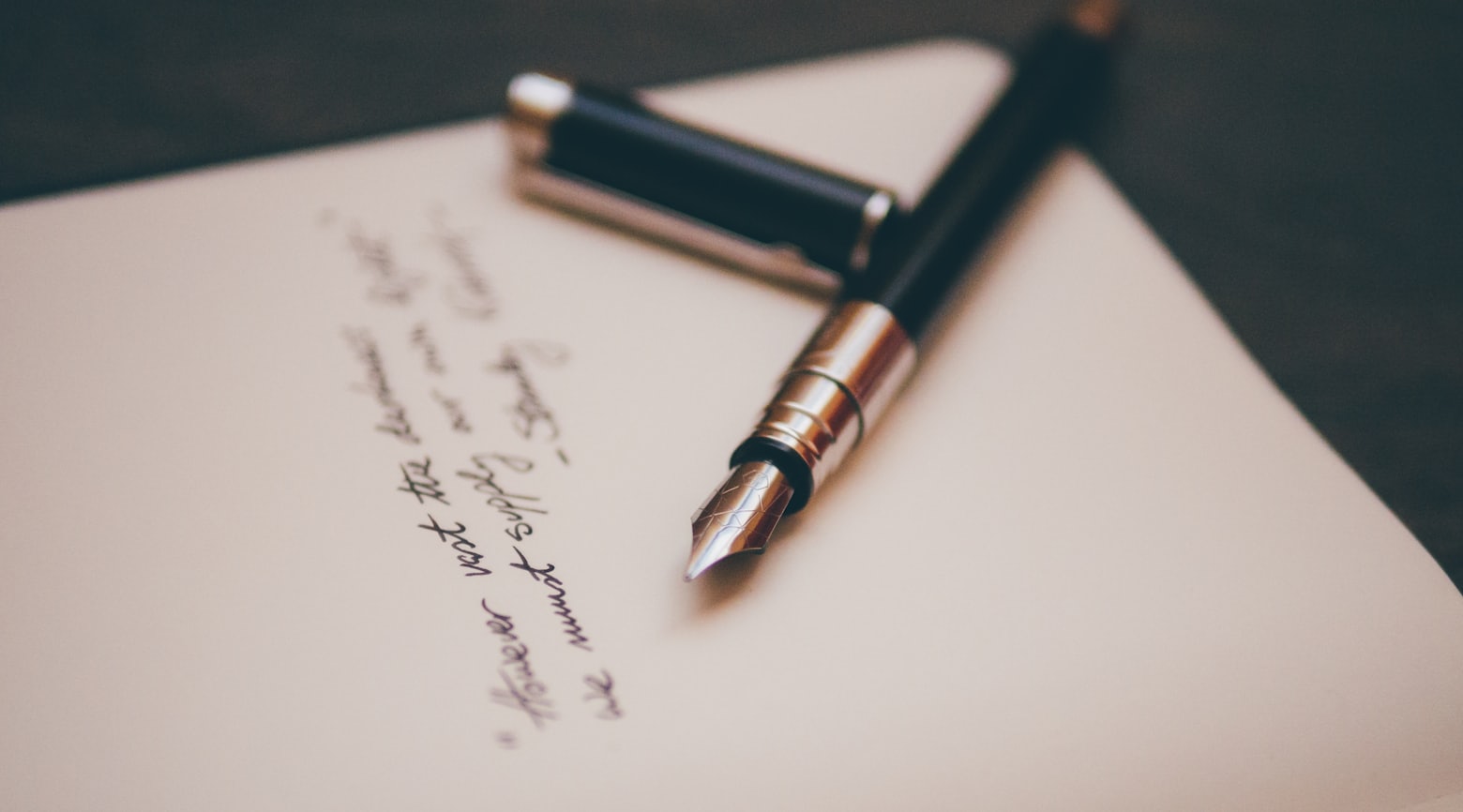「なしのつぶて」の要点
-
意味:「返事がないこと」
-
由来:「投げられた小石は決して投げた方には返ってこず行ったきりであること」
-
例文:「卒業以来初めての同窓会の案内を出したが、半数以上は「なしのつぶて」だった。」
-
類語:「無反応」「音沙汰なし」
-
英語:「heard nothing」
なしのつぶての意味は「返事がないこと」
(画像:Unsplash)
「なしのつぶて」とは「返事がないこと」で、「応答がない」「無視されている」という相手を非難するニュアンスが込められています。相手に連絡をしたが、相手から全く反応がない状態のことをいいます。 「なしのつぶて」は漢字では「梨の礫」と書きます。「梨」は果物の「梨」で、「礫(つぶて)」は「投げる小石」のことです。 「なしのつぶて」は連絡手段を問わず使えます。郵便でも、電話でも、LINEでも、とにかく返事が返ってのないのは「なしのつぶて」です。
なしのつぶての語源
(画像:Unsplash)
「なしのつぶて」の漢字は「梨の礫」でした。 「礫(つぶて)」は投げる小石のことですが、投げられた小石は決して投げた方には返ってこず行ったきりです。「なし」はもともと「無し」の意味でした。返ってこない「礫」と「無し」を重ねて応答がない様を強調しているのです。 ただ、「無しの礫」では何もないものを投げることになってしまいますので、語呂合わせで「梨」という同じ音の漢字があてられました。このように日本語には字を見ただけでは意味が連想しにくい言葉が幾つか見られますが、「なしのつぶて」もその中の一つといえます。
なしのつぶての使い方と例文
(画像:Unsplash)
「なしのつぶて」は連絡手段を問わず使えますから、様々な使われ方があります。「なしのつぶて」は応答がない様を客観的にいっているようで、実は何も返事を返してこない相手を非難しているニュアンスがあります。 以下で例文を二つ見ていきますので、その辺のニュアンスをくみ取ってください。
例文①連絡に対して反応がない
まずは何らかの手段で連絡をしたにも関わらず何の反応もない場合の例文です。
例文
-
LINEの既読スルーも「なしのつぶて」と受け止められるかもしれない。
-
卒業以来初めての同窓会の案内を出したが、半数以上は「なしのつぶて」だった。
最初の例文はおそらくハガキかメールで同窓会の連絡を出したのでしょう。それに対して何らかのリアクションがあったのは半数以下であったと嘆いています。 二番目の例文はLINEのよくあるケースです。既読の表示はされるのだが、そのままスルーされ何の返信も返ってこない状況です。
例文②期待する人から連絡がこない
当然何らかの連絡があっても然るべきなのに、何の連絡もない場合にも「なしのつぶて」が使われます。
例文
-
彼とは3年前に何でもない行き違いで別れてしまいその後「なしのつぶて」になってしまった。
-
今日は私たちの30年目の結婚記念日なのに上京した息子からは「なしのつぶて」だ。
二つの例文では何か連絡があるはずだと期待する自分がいます。それなのに期待に反して何の連絡もないことをさみしがっています。このように、こちらからの連絡に対する返事が来ない場合以外にも「なしのつぶて」を使う場合があります。
なしのつぶての類語
(画像:Unsplash)
「なしのつぶて」に関する意味や語源、よく使う例文をここまで見ていました。もう自信をもって「なしのつぶて」が使えるのではないでしょうか。 ここからは「なしのつぶて」の類語である「無反応」と「音沙汰なし」を見ていきましょう。
無反応
「無反応」はその字のとおり「反応がない」ことですから、「なしのつぶて」の類義語といえます。 「無反応」も「なしのつぶて」も反応がないという状態を客観的に表す表現ですが、背後に少し相手を非難するニュアンスを持っていることも共通しています。 「無反応」と同じように使われがちな言葉に「無視」がありますが、こちらは非常に意思が感じられる言葉で、わざと反応しないという悪意が全面に出ています。「無反応」や「なしのつぶて」とは全く違うニュアンスになりますので使い方に気を付けましょう。